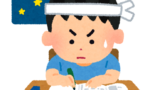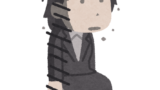博士が闘病生活を語るにあたり|
私は2019年の夏にうつ病で休職し、それ以降自宅療養を兼ねて主夫をしています。
最近、ようやく元気がでてきて、本屋で鬱について書かれている本を手にとるようになりました。
これを実行すれば、これを食べれば、これを聞けば鬱は治りますなどと素晴らしい内容の書籍を多く目にしました。
これらを書かれた方々は無事に寛解(克服)を迎えたゆえに、その経験談やノウハウを書かれていました。
ただ、残念ながら私の場合は回復過程にはあるものの、これらの本にあるような寛解の状態には至っていません。
まだ何か重くのしかかるものたちと格闘しています。何をどうすれば回復に向かうのか、よくわかないのが本音です。

最近、元日本ハムの新庄選手がトライアウトにチャレンジしました。
残念ながら獲得球団は現れませんでしたが、彼のチャレンジは大変共感を呼びました。
松岡さんが「何が今欲しいですか?」と聞くと、新庄さんは「逆境ですね。常に人生に逆境が欲しいです。」と答えました。
彼の強さ、前向きさにか感服させられました。
ただ、実際にこういった前向きな方がすごく身近にいると、負担に感じてしまう方も多いのではないかと思います。
私の場合、テレビで活躍するコメンテーターの強気コメントや友達の成功体験も聞くと、それだけで辛くなって逃げ出したくなることがあります。
私も彼らのように強気で前向きに生きなければならない、といった強迫観念に襲われるような気がして、自分の現在の姿があまりにも情けなく、みじめに感じてしまいます。

実は、今年の夏からしばらくTwitterをやっていました。心の病と闘っている方の多くは家族や友人、同僚に自分の辛い気持ちを伝えたい、理解してもらいたいという気持ちがあると思います。
同じ心の病と格闘している方々のつぶやきや俗にいうネガツイ(ネガティブツイート)を目にすると、自分がなんとなくそのコメントに共感して、世の中には自分と同じ気持ちの人がいるんだ、という安心感と仲間意識を感じました。
または自分がつぶやいたネガツイ対して返事をいただいたときには、自分の気持ちを理解してもらえたんだ、というちょっとした喜びがありました。
私にとっては初めての経験で、大きな支えになりました。
まだ、寛解していない私のような者が人に読んでもらう文章を書いていいものか、と疑問には思います。
ただ、心の病というのは健常者には理解しがたい部分があって、逆に病を持っている者同士は共感できることも多いような気がしていて、場合によっては私の言葉でも共感してくれる人がいるのではと思いました。
そういった方の手助けになればと考え、今日に至るまでの過程や今の心境、寛解に向けたリハビリ、就活の状況を書かせていただきたいと思います。
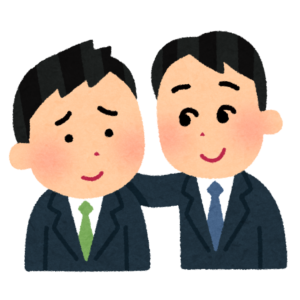
悲惨な日本のアカデミア業界
リストラという北風が吹き荒れる中、私は新しいラボに移籍しました。
移籍先の前プロジェクトでは数百億(?)という予算を使って、大きな施設、研究棟、数百人に及ぶスタッフを確保していましたが、私が赴任したときにはそれらは不良債権化し、しばらくはコピー用紙すら買えないような状況でした。
まさに研究バブル崩壊といった感じでした。
ただ今考えると、この段階でアカデミアを辞めることになった方々はかえってよかったのではと思います。
ほとんどの方が35~40歳くらいと民間企業では十分に採用していただける年齢であったのと、まだ基礎研究に民間企業もかなりの額を投資をしていた時代でした。

このころからアカデミアに割り振られる国家予算が年々減っていき、そのわずかな予算も競争的資金として割り振られることが多くなりました。
多くの研究者は研究機関個別の予算ではなく競争的資金で雇われるようになりました。
また、この新しい研究機関では、自分の成果となる研究とは別に組織が請け負った業務(組織で獲得した競争的資金に関する仕事)があり、それぞれ働く割合が決められていました。
そのため、業務を一定時間は行わなければならず、個々の研究を圧迫しはじめました。このころも、自分の研究をするために予算(科研費)というものを自分自身で申請するのですが、採択されると上司から嫌味を言われました。
というのも、科研費が採択になるとそれに働く割合を与えなければならず、組織の仕事の割り当てを減らすことになります。
つまり上司の仕事(業務)を部下に割り当てることができなくなるためです。
上司からすれば業務は上司自身の成果に直結するので、是が非でも成功させたいところですが、部下からするとどうでもいい、というのが正直なところでした。
私は何とかこの組織で生き残りたいと思い、徐々に業務は避けて、その中でもできるだけ論文になりそうなものだけ行うようになりました。
結果としてこういった考え方を持った研究者が組織や業界に生き残っていくため、日本のアカデミアにおける個人主義者が増加してしまったのだと思います。
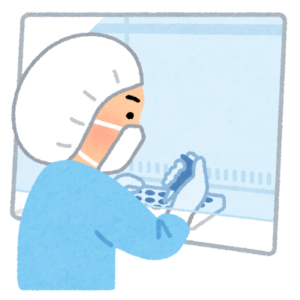
アカデミアの人間関係
予算の締め付けが厳しくなってくると徐々にラボ内の人間関係の構図も変化してきたような気がします。
所属している研究者はボス公認で自分のテーマだけを行うことが許される人と雑用や業務を押し付けられる人にわかれてきました。
当然ながら雑用を押し付けられる”いい人”は成果(英語の論文)を出しにくくなります。論文がなければ外部資金も取得しにくくなるし、自分の研究もすすめられなくなる。
研究者として負のスパイラルに陥ります。任期制の研究者というのは年に一度、プロ野球のような契約更改があるのですが、論文や予算がない研究者は翌年のリストラの対象になったり、降格させられるといったケースが目立つようになりました。
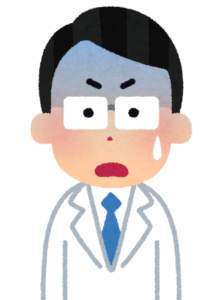
このような状況になってくると隣にいる人はライバルというより”敵”になります。
このような殺伐とした世界で育ってしまった30代前後の若い世代は特にそうなのてわすが、研究者としてより人間としては信じがたい人格の者だけが残ってしまったように感じました。
当初はそういった人達と距離をおいて仕事をすることができましたが、徐々に人が減っていくと、さけるにもさけられないほどの距離にとんでもない人がいた、という状況になりました(詳細は後ほど)。
研究者としての仕事もままならず、人間関係も築きにくくなってくると、普通の感覚をもった人間はやりにくくなっていきます。
私が普通かどうかはわかりませんが、居心地の悪さは強く感じていました。

さらに、このころからボスにとっての論文一本の価値と研究員にとっての論文一本の価値の違いも徐々にかけ離れるようになりました。
ボスはシングルヒット級の論文を数多く出すより、ホームラン級の論文を一本だすだけのほうがインパクトが大きいため、よりビックな雑誌向けの論文を優先するようになりました。
そのため、多くの研究者の論文の投稿が大幅に遅れ、場合によってはお蔵入りにもなりました。
論文を出しにくくなるという研究環境の悪化は当然ながら研究者に強いストレスを与えました。
私も世界で初めての研究成果を得られたので、それをすぐに発表したかったのですが、ボスがもたもたしている間に先を越されてしまいました。
ボスにとっては他にも成果の選択肢がありますが、個々の研究者にとっては何年もかかって得られた唯一の成果であり、それが破綻するとなると、とてつもない精神的なダメージをうけます。私の精神は再びむしばまれていきました。
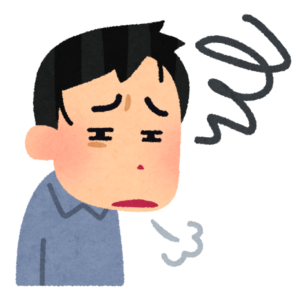
うつの兆候
私は業務的な研究をそれなりにこなしながらも、やはり自分の成果となる論文に力をいれていました。
なんとしてもよい論文を出してアカデミアで活躍したいという気持ちがありました。前にも書きましたが、努力の甲斐もあって世界初という成果を出すことができ、私はこの成果であれば良い雑誌に論文を掲載できるのではとたいへん期待しました。
ところが、ボスの対応があまりにもお粗末で、最初のタイトルをきめるだけで二週間もかかり、その後も思うように論文作成をすすめることができませんでした。
通常なら論文は1~2か月である程度の形になっていくものですが、会えるのが数週間に一度、あったとしても文章内の単語一つ一つに時間をかけるので、一行すすめるのに30分程かかっていました。
さらに前後のストーリーや論理的な記述を考えていくと膨大な時間がかかりました。この過程は英語の良い勉強にはなるのですが、ライバルとの競争を考えるととてつもないストレスを感じました。
そうこうしているうちに恐れていたことが起こりました。
ある朝、デスクでweb上で公開になった論文をチェックしていたところ、海外のグループから私のまとめている内容とほぼ同じ論文が発表されていることがわかりました。
このときの衝撃はすさまじいものがありました。
人生最大のショックでした。
私は動揺して手が震え、心臓が高鳴り、仕事が全く手につかなくなりました。これで研究人生が終わってしまったと感じました。
目標を失ってしまった私は徐々に何事にもやる気が出なくなり、楽しかったことが楽しめなくなりました。

通院生活と厳しい研究生活
実は職場の定期の健康診断の際にメンタルチェックの問診していただいた産業医から臨床心理士のカウンセリングをすすめられていたので、私は定期的にカウンセリングを受けるようになっていました。
職場では日常会話をできるような環境ではなくなっていたので、時には仕事のことや家族のことを洗いざらい話す場として、時には客観的な意見をうかがう場として、時にはハラスメントのジャッジ役として、私にとって貴重な時間となりました。ある日、家族で郊外のうどん屋に車で向かっていました。
何度か行ったことがある店で普通は迷うことなどはないのですが、運転しながら頭の中が論文のことで一杯になって、自分がどこにいるかわからなくなってしまいました。
私の人生で初めての経験でした。そのことをカウンセラーの先生に話すと、心療内科の受診をすすめられました。
私は薬を飲めば気分が少しでも楽になるだろうしやる気も出てくるのでは、と気楽な気持ちで受診してみることにしました。![]()

心療内科は自宅のすぐそばにあったのでとりあえずそこに行くことにしました。
普通の病院とは何か違う落ち着いた感じの待合室で大きなモニターでは鉄道や世界遺産などの映像が静かに流れていました。
そのうちに名前が呼ばれて診察室に入っていくと比較的若い男性の医師が対応してくれました。
初診は仕事と家庭の様子、論文のこと、パニックのことを細かに話しました。日常的に症状があるわけではないので、安定剤くらいは処方されるのではと考えていました。
「その医師はうつっぽいですね、お薬を出しますので飲んでみてください」と、ある抗うつ薬が処方されました。
さぞ気分は改善するのだろうと期待して1ヶ月間、毎日飲み続けました。
しかし、このときは副作用も全くでることもなく、そのかわりに体調や気分が上向くということもありませんでした。
毎回の診察では、「元気だったころを10割とすると、今の気分は何割?」と聞かれるので、私は3ー4割と答えていました。
医師はこれを押し上げようと、その後もいくつかの抗うつ薬を処方してくれました。
しかし、気分的な改善には繋がりませんでした。
仕事では相当のストレスがかかっていたので、薬はその下支えとして効いていたのだろうと思いますが、その当時は全く気がつきませんでした。
その後も仕事のストレスが気分を押し下げて、薬でそれを下支えをする、という低空飛行の状態が数年間続きました。
現在のように何かに頭を常に支配されて頭を抱えて唸るというところまでは悪化してはいませんでしたが、何かをやろうという気力は失われていました。
それなりに出勤し、それなりに実験を続け、それなりに論文を書き、という生活を送っていました。

その後、組織の改編がありました。私の任期がいったん切れ、次のプロジェクトに再雇用されることになりました。
それに伴って所属組織が変わり、直属のボスもかわることになりました。このことが結果として私をさらに追い込むことになります。
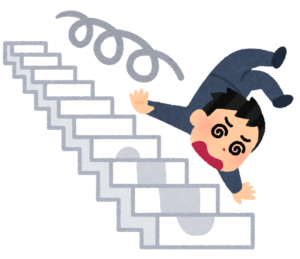
こちらへ続きます。
うつ病体験記